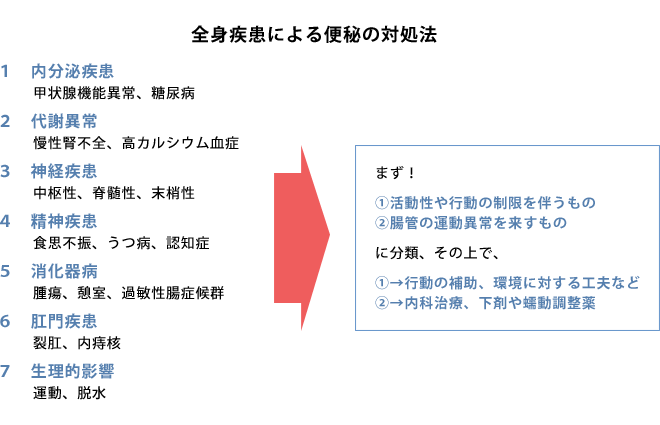下剤に頼らない排便ケア
排便コントロールのアプローチ
全身疾患をもった高齢者に対する便秘対処法
医療法人社団俊和会 寺田病院 神山剛一
教科書には、便秘の原因となる全身の病気がたくさん書いてあります。糖尿病、甲状腺機能低下症、慢性腎不全などなど…、各疾患の特徴に応じて便秘対策を講じようと思ったらきりがありません。しかも、全身疾患を持っているからと言って、必ず便秘になるわけではないですし、ましてや、それぞれの病気においても、病気の進行度や罹患時期が違えば、当然、便秘への影響も異なります。従って便秘対策は個々の病気について検討するのではなく、個人個人に応じて対処すべきなのです。
全身疾患を持った人の「便秘」は、大きく二つに分けて考えるとよいでしょう。1つは、その人がどの程度の活動制限を伴っているかどうかです。例えば、ベッド上安静や寝たきりの方は、自由にトイレに行くことができないので、排便に支障を来します。或いは指の関節が思うように動かせなければ、衣服の着脱において制限されるので、トイレ行動に障がいが生じます。こういった場合、障がいに応じて排泄行為を援助します。二つ目は、腸のはたらきが問題あるかどうかです。いわゆる蠕動運動が悪ければ便の出も悪くなるので、蠕動運動を促進する薬が必要になるでしょう。食事制限等で食事摂取が不充分の患者も同様です。栄養を吸収するという腸のはたらきが阻害される訳ですから、健康な人に比べて便が出なくなるのは当然です。
このように便秘に対するアプローチは疾患によって区別するのではなく、その全身疾患が患者さんの活動性や腸のはたらきにどのように影響しているのかによって分類するのです。活動制限や行動制限による障がいと、内臓のはたらきの問題と分けて見ることができれば、自ずとどのような対処をすればよいかが浮かんできます。