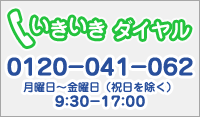
関連情報
ライフリーの商品情報、大人用紙おむつの選び方、医療費控除など介護についての情報をご紹介
病院・施設向けのライフリー商品をご紹介。店頭用との早見表もあります。
本サイトがめざすもの:ユニ・チャーム排泄ケア研究所
排泄ケアが語られる時、おむつを安易に使用しないことが常に戒められてきました。介護者の都合でおむつを使うことは高齢者の自尊心を傷つけたり、排泄の悪化につながることがあるからです。
排泄の障がいとは、トイレでうまくできなくなることです。始めから、できないのではなく、たまに失敗する、ときどき失敗する、ほとんど失敗する、まったくできない、というように段階的に進行するのが一般的です。それは幼児の「おむつはずれ」のステップに似ています。ただ発達と衰退のベクトルが逆方向を向いているだけです。子どもたちは、トイレで上手に排泄できるようになるまで、おむつをしています。乳児のときはテープ止めタイプのおむつをし、つかまり立ちができるようになる頃からパンツタイプのおむつ(紙パンツ)に変えてもらいます。そして、トレーニングパンツやおねしょパンツを利用し、やがて卒業していきます。大人用のおむつも、障がいの進行やケアの目標に合わせて、使い分けができるように、豊富な種類が揃ってきました。在宅で使用されている紙おむつの60%以上が、「寝た姿勢で使う」テープタイプから、「自立排泄を促進する」パンツタイプ(紙パンツ)に変わってきました。それは「まったくできなくなる」ギリギリのところまで、「トイレで排泄させてあげたい」と願う家族の支援の表れでもあります。
排泄ケアの考え方が進歩することでおむつも変わりました。また、おむつが進化したことで、排泄ケアも、被介護者の気持ちを大切に、進歩してきました。ケアの技術と用具の開発が互いに影響し合うサイクルが、これからの排泄ケアをさらに変えていくことを願って、このサイトを制作しました。
寄稿:船津 良夫(1998年~2017年 ユニ・チャーム排泄ケア研究所 主席研究員)
参考文献
- 佐々木由惠、荒尾晴恵「排泄介護技術」(ユニ・チャーム排泄ケア研究所 1997)
- 船津良夫「紙おむつの科学」(ユニ・チャーム排泄ケア研究所 1997)
- (社)日本衛生材料工業連合会 編「紙おむつ Q&A」(日本衛生材料工業連合会 1999 第4刷)
- 大島伸一 執筆・監修「高齢者排尿管理マニュアル」(愛知県健康福祉部高齢者福祉課 2001)
- 岡村菊夫、後藤百万、三浦久幸、山口 脩、内藤誠二、長谷川友紀、大島伸一「高齢者尿失禁ガイドライン」
- 加藤久美子、近藤厚生、斉藤政彦「行動療法」「尿失禁治療のキーポイント」(金原出版 1997 第2刷)
- 奥井識仁、奥井まちこ著「在宅でみる排泄介護のコツ」(南山堂、2002)
- 鎌田ケイ子 編著「在宅用・フローチャート式 ケアプランの立て方」(高齢者ケア出版 2002 第4版第1刷)
- 鎌田ケイ子「尿失禁の看護用具」「尿失禁ケアマニュアル」(日本看護協会出版会 1998 第1版3刷)
- 牧野美奈子、市川 洌 著「排泄の知識と用具の選び方」(<財>東京都高齢者研究・福祉振興財団 2001)
- 今丸満美「訪問看護による排尿管理と介護保険」(排尿障害プラクティス vol.10 No.4 メディカルレビュー社 2002)
- 老人泌尿器科学会 編「高齢者・排尿障害マニュアル」(メディカルレビュー社 2002)
- 大田仁史 著「脳卒中 在宅療法の動作訓練」(アビリティーズ総合研究所 1998 再版)
- 大田仁史、三好春樹 監修・著「新しい介護」(講談社 2003)
- 中村はるね 監修、からだ系コイダス編集部 編「知ってホッとする『からだ系』の疑問」(講談社+α文庫 2000)
- 並河正晃 著「老年者ケアを科学する・いま、なぜ腹臥位療法なのか」(医学書院 2002)
ユニ・チャーム排泄ケア研究所
全国の施設・病院で排泄ケアの実態を調査しながら製品開発検証、紙パンツを使ったトイレ誘導・自立排泄支援の普及活動を展開。一般市民向けの介護予防教室、在宅介護に携わる専門職や家族介護者向けのおむつ教室も開催。



