排泄ケア研究発表
もれないおむつのあて方への取り組み
結果
船津氏の研修会は65名が参加し、ケアアドバイザーによる研修会は5病棟スタッフ全員が参加した。基本のあて方を実施してから、おむつの使用枚数は実施前では最大7枚を重ねて使用していたのに対して、実施後は2~3枚の使用が定着した。(表1)基本のあて方を実施してから、ケアアドバイザーにおむつ交換をみてもらったところ、基本のあて方は習得されていると言われた。
| 従来のあて方 | 基本のあて方 | |||
|---|---|---|---|---|
| 女 | 男 | 女 | 男 | |
| 尿とりパッド | 1~3 | 1~4 | 1 | 2 |
| テープタイプ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ロング/布おむつ | 1~2 | 1~2 | 0 | 0 |
調査の対象患者数は、57名であった。
もれの件数の比較では、尿もれは、実施前では70件、実施後では42件みられた。便もれは、実施前では87件、実施後では34件であった。
尿もれのあった人の実施前後の変化は、従来のあて方では31名(男性7名、女性24名)がもれていた。そのうち21名(男性4名、女性17名)は基本のあて方にしてから改善された。しかし、10名(男性3名、女性7名)には、もれがみられた。また、もれが重ねあての時にはみられなかったが、基本のあて方にしてからみられるようになった患者が6名(男性2名、女性4名)いた。基本のあて方にしてからも尿もれがみられた人の特徴としては、尿量が多い人、動く人やおむつ触りがある人、拘縮がある人、男性で陰茎が小さい人がいた。
便もれのあった人の実施前後の変化は、従来のあて方では26名(男性8名、女性18名)がもれていた。そのうち13名(男性7名、女性6名)は基本のあて方にしてから改善された。しかし13名(男性1名、女性12名)には、もれがみられた。また、もれが、重ねあての時にはみられなかったが、基本のあて方にしてからみられるようになった患者が3名(男性0名、女性3名)いた。
便もれがみられた時の便の性状は、実施前は、泥状便が55件と最も多くみられ、次いで水様便が19件、軟便8件、普通便、硬便はそれぞれ1件、記入なし3件であった。実施後は、泥状便が19件、水様便が16件であった。(表2)
尿とりパッドの使用枚数については、5病棟の尿とりパッドの納品数は、4月168袋、5月164袋、6月164袋、7月120袋であった。(図1)
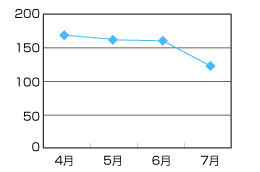
図1. 5病棟の尿とりパッドの納品数
| 重ねあて | 基本のあて方 | |
|---|---|---|
| 泥状便 | 55 | 19 |
| 水様便 | 19 | 19 |
| 軟便 | 8 | 27 |
| 普通便 | 1 | 0 |
| 硬便 | 1 | 0 |
| 記入なし | 3 | 0 |
考察
波多野は1)「経験を中心とした自己成長だけに頼らず、効率的な訓練によって科学的に知識・技術を習得し、発展させることが必要である。」と言っている。講義と実技の研修に参加する事により、基本のあて方を理解することが出来、また、重ねあてのデメリットを知る事が出来た。これにより、重ねあてをしないという意思統一が出来たと考えられ、研修は、非常に有効だったと言える。
全体に尿もれ、便もれの件数が減ったという事から、汚染による患者への不快・負担と、もれによる更衣の時間、スタッフの労力が減ったと考えられる。基本のあて方を実施した7月は、重ねあてをしていた4月に比べて、一ヶ月で48袋、パッドの枚数でいうと2160枚、金額で換算すると81600円の減少がみられた。この事から、尿とりパッドにおいて病院のコスト(おむつの廃棄量)削減につながり、患者、家族の金銭的負担も軽くなったと考えられる。また、資源の面でもパッドが有効に使われており、無駄がなくなった事で、地球環境に優しいと考える。尿もれがないという事は、スタッフが技術を習得し、確実に実施できるという自信につながっていると考えられる。それは、尿もれさせてしまい、申し訳ないという患者に対する負い目がなくなり、スタッフの精神的負担が軽減したと考えられる。これらの事から、基本のあて方は、もれに対して効果が大きいといえる。
しかし、基本のあて方にしてから尿もれがみられた人や以前から尿もれが変わらない人がいる事から、必ずしも基本のあて方がすべての人によいわけではないと考えられる。基本のあて方で、もれのみられる患者には、尿量が多い、陰茎が小さい、拘縮している、自分で触る、自分で動くなどの特徴があった。男性が、女性に比べてもれやすいのは、陰茎にパッドをまく事で、尿道口に密着させにくいことや、排尿時、パッドの中で陰茎が動くといわれており、あて方に注意する必要があるといえるのではないか。そのためには、パッドがずれないようにテープタイプでしっかりおさえるあて方の工夫が必要であるといえる。また、パッドで陰茎をきちんとまく事ができない患者は、吸収面を広くするあて方や、女性と同様のあて方をするなどの工夫が必要である。男性のもれの多かった原因には、おむつのあて方が不適切であった事も考えられる。ポイントをふまえたあて方を習得する必要がある。おむつ触りをする患者に対しては、排泄パターンを把握し、交換時間や、おむつ使用の必要性を検討し、可能ならば、トイレ誘導や尿器の使用を考えていく必要がある。股関節の拘縮がある場合は、股関節の隙間をぬうようにパッドを動かし、陰部に密着させる方法もある。
実施前は、すべての性状の便でもれがみられたのに対し、実施後は泥状便と水様便のみしかみられなかった。これは、重ねあてをなくした事で、隙間がなくなったからであると考える。しかし、実施後も便もれは、泥状便と水様便の時に圧倒的に多く、これは、患者の便秘に対して下剤を使用して、排便コントロールをはかっており、その結果、下痢をしているのではないかと推測する。男性は、臀部にあてているパッドは、便のみをキャッチしているのに対し、女性は、尿と便両方をキャッチさせる必要があるが、便が柔らかすぎると、パッド内で伸びて、尿と混ざって十分吸収せず、もれてしまう。この事からも、形のある便に調節していく事が便もれ対策につながると考えられる。
船津氏は2)、「『もれない工夫』は高齢者の自尊心を尊重するケアにつながります。」と言っている。私たちはこれからも患者主体のケアを提供するために、今後は以下の課題に取り組んでいく必要がある。
- 今後も定期的におむつ、排泄に関する学習会と、学習内容をスタッフに広める研修会を定期的に行う必要がある。
- 基本のあて方も、もれる人にはアセスメントを行い、あて方の工夫、適切なおむつの選択を行う必要がある。
- 排便コントロールが必要である。
結論
- 研修は、おむつ交換の知識、技術の向上には有効である。
- 基本のあて方は、効果があった。
- 一部、基本のあて方に当てはまらないケースがあった。
- 今後の課題が見出せた。
引用/参考文献
引用文献
- 波多野梗子:系統看護学講座 専門1基礎看護学1看護学概論、医学書院、P235、1999
- 船津良夫:在宅介護のための排泄ケアナビ、ユニ・チャーム(株)
参考文献
- 島崎幸子、指田則子、渡部綾子:おむつのあて方の見直しを通して、重ねづかいの認識を変える-おむつを重ねなくても大丈夫-、第35回看護管理、P316~318、2004
- 山崎節美・中野千登世・原田愛・藤井久美子・松永早苗:尿意伝達困難患者のおむつのあて方と時間の検討、臨床看護、第30巻大8号、P1222~1231、2004
医療法人社団映寿会 映寿会みらい病院
地域に開かれた病院として、地域の医療ニーズを反映した方針を策定し総合的な健康づくりをお手伝いします。
所在地
〒 920-8201 石川県金沢市鞍月東1-9
電話
076-237-8000



