紙おむつとは
もれてしまう使い方
障がいのある高齢者におむつをきちんとあてるのは、大変難しい事です。
特に、股間部位にすき間を作らないようにあてること、腰骨の上まできちんと上げることには苦労します。
しかし、紙おむつの機能はあて方によって大きく左右されます。
紙おむつの機能が充分に活かされないケースを知り、効果的に使うよう心がけましょう。
ズレ・たるみ・すき間ができてしまう
- 紙おむつ(アウター)がずり落ち、背中にすき間ができ、おしりと股間にもすき間とたるみができてしまっている。
- この状態で寝ると、背中部分からのもれが起きやすくなる。
- 股間部分の紙おむつは肌に固定されなくなり、尿道口からも離れ、ずれたりよれたりする。そのため紙おむつの吸収機能、保水機能が活かされない。
- 太もも周りの立体ギャザーが、肌に接し、立った状態を保てないため、太もも周りにもすき間ができ、もれを防ぐギャザーの機能が活かされない。太もも周りのすき間からもれてしまう。
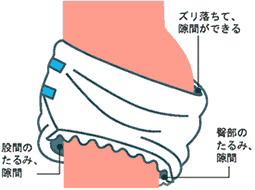
なるべくやめたい、重ね使用
もれが発生すると、パッドの吸収力が足りなかったと考え、もれを防ぐ目的で、何枚ものパッドを重ねてあてる「重ね使い」が行なわれることがあります。
しかしこうした使用法は、吸収機能や保水機能の補強にはほとんどなりません。逆に、下着や紙おむつの中で、パッドの重なりによるすき間を作ることになり、かえってもれやすくなってしまいます。
紙おむつ・パッドには「吸収面」と「防水面」があり、吸収面以外から吸収されることはなく、「防水面」の下に「吸収面」を敷いても尿は下に落ちません。広い面積の、吸収力の高いパッドと使い分けることが賢明です。
また、夜間の介護負担を軽減する目的などで、何枚かのパッドを重ねてあて、汚れたら、順番に抜き取っていく使い方をするケースがあります。重ね使用はゴワゴワして動きにくく、つけている人にとっては不快ですから、なるべくやめたいものです。
ただし、拘縮(筋肉が固まっている状態)があり、足が曲がらなかったり伸ばせない、足が開かない方や、肥満の方が横向きに寝て睡眠する場合は、おなかや足の肌の溝に尿が入り込み、糸が走るように尿が流れ出ることがあります。こうした箇所にもう1枚パッドをあてて、尿の流れや広がりを防ぐ使い方は効果があります。
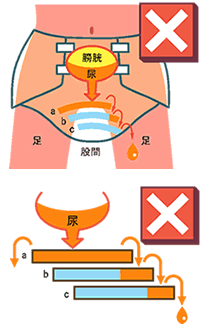
パッドの重なりですき間ができ、
横などにもれ出すことが多い。
吸収機能や保水機能の補強にはならないので、
重ねづけはできれば避ける。

